第27回 DIHAC 研究会 報告 27th DIHAC cross-cultural exchange meeting analysis report (Japanese)
第27回 DIHAC異文化交流会議 実施報告書
食事と友情を通じたデジタルインクルージョンの推進:米国ミシガン州の「バーチャル・コネクション」とシンガポールの「コミュニティ・フリッジ」に学ぶ
後藤夕輝, 小柳祐華, ミョーニエンアング
Report in English Report in Thai Report in Spanish Report in Vietnamese
デジタル・インクルーシブ・ヘルシー・エイジング・コミュニティ(DIHAC)は、主に日本、韓国、シンガポール、タイを中心に展開されている異文化研究であり、現在、関連ネットワークやコラボレーションを通じてインドやマレーシアにも拡大しています。プロジェクトの一環として、私たちは隔月で異文化会議を開催し、世界各地のヘルシーエイジングとデジタルインクルージョンに関する革新的な取り組みや地域実践を共有しています。第27回DIHAC異文化交流会議では、米国ミシガン州立大学とシンガポール国立大学から演者を招き、地域社会における食事や食糧支援プログラムを基盤とした社会的つながりが、高齢者のデジタルおよび社会的包摂をどの様に促進するかについて議論しました。本会議は、2025年2月20日に開催されました。
DIHAC研究の主任研究員であるMyo Nyein Aung准教授が参加者を歓迎し、歓談を交えながら会議を開始しました。その後、議長であるHelpAge IndiaのCEO、Rohit Prasad氏に進行が引き継がれました。Myo博士とPrasad氏は、昨年、国連アジア太平洋経済社会委員会(UNESCAP)の会議(中国およびインドネシア・バリ)にも参加しています。Prasad氏は、社会事業およびビジネス分野で長年の経営経験を持つ著名な経営幹部です。現在は、高齢者の健康と福祉の向上を目指すHelpAge Indiaの主要メンバーとして活躍しています。本会議には、日本、韓国、シンガポール、タイ、マレーシア、ラオス、中国、香港、インド、ベルギー、ウクライナ、ヨーロッパ、米国から、官民の関係者、UNESCAPおよび世界銀行の職員、医師、健康長寿の専門家、グローバルヘルス、公衆衛生、社会老年学、ジェロンテクノロジーの分野の研究者や大学院生など、40名以上が参加しました。
議長からの挨拶として、Prasad氏は、DIHAC研究会議が時差や地理的な隔たりを超えて高齢化研究者や専門家が協力する取り組みであることに触れました。続いてPrasad氏は、HelpAge Indiaがインドにおける健康的な高齢化を促進することを目的に、地域レベルのサービスから研究や提言活動まで、社会経済的に脆弱な高齢者層のために活動していることを簡単に説明しました。その後、彼はインドにおける現在のデジタル化、都市部と農村部のデジタル格差、そして高齢者への影響について強調しました。そして、健康とデジタル技術が融合する時代において、デジタル時代の世代差別を最小限に抑え、ユーザーフレンドリーな設計とプライバシーを推進することが重要な課題であると訴えました。これは、ヘルシーエイジングの10年に向けた重要なメッセージです。
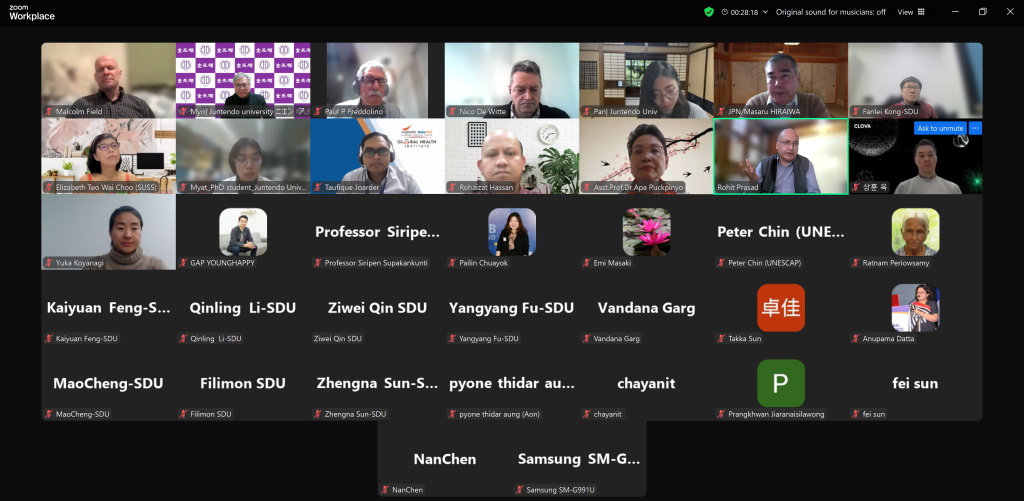
図:第27回DIHAC会議における議長のRohit Prasad氏、演者、海外からの参加者、DIHAC研究チーム
プレゼンテーション1:バーチャルなつながり:支援が届きにくい高齢者のデジタルリテラシー向上のための3つの戦略
最初の演者は、米国ミシガン州立大学社会学部ソーシャルワーク学科教授のPaul P. Freddolino博士でした。Freddolino博士は、人口の19.3%が65歳以上で、高齢者の支援に16の地域機関が取り組んでいるミシガン州のコミュニティで実施されているデジタルエンパワーメントプログラムの3つの戦略を紹介しました。ミシガン州の雪深い地域では、一人暮らしの高齢者の基本的なニーズを満たすために、配食サービス(Meals on Wheels)の取り組みが行われています[1]。2020年以降に開始されたデジタルエンパワーメントプログラムは、テクノロジーが社会的孤立を軽減できるという考え方と、高齢者は親しい信頼できる人(ウォームエキスパート)の支援を受ければデジタルテクノロジーの障壁を克服できるという考え方に基づいています[2]。以下に3つのプロジェクトについて詳しく説明します。
プロジェクト1は「バーチャルテーブル」モデルと呼ばれ、信頼のおける配食サービス(HDM)の配達員(ウォームエキスパート)が、HDMの受給者を対象にデジタルリテラシー研修プログラムを実施しました。色刷りの教材とインターネットにアクセスできるタブレットが参加者に配布されました。8~12週間のコアとなるICTスキルコースでは、基本的な機器の使い方、ソーシャルコミュニケーション、参加者が選択したトピックがカバーされました。その後、6~8週間の遠隔医療コースが続きました。さらに、ボランティアとの毎週のチャットと、Zoomを介した月1回の交流会もプログラムに含まれています。
評価結果によると、中間地点で参加者がさまざまなデジタル技術を利用する回数と頻度が大幅に増加し、その傾向は事後テストまで持続しました。同氏は、コンピューターの自己効力感、孤独感、その他の心理的パラメータの変化は、トレーニングをさらに強化することで観察されることが予想され、スキルは時間とともに向上すると説明しました。信頼関係は、デジタルリテラシープログラムへの参加、継続、満足度を高めるのに効果的であることが分かりました。デジタルリテラシーに加えて、高齢者はコーチとの社会的つながりによる恩恵をうけます。コーチ、ボランティアの人材、経済的に持続可能な計画などの課題は、今後の実施に向けて考慮する必要があります。
続いて、デトロイトの高齢者センターで、集団給食の受給者(グループでの食事)を対象に「バーチャルテーブルII」が実施されました。参加者は、スマートフォンを所有する支援やサービスを必要とする低所得の高齢者でした。携帯電話を利用した遠隔医療コンテンツは、バーチャルテーブルの修了者との参加型アプローチで開発されました。デジタルリテラシーのトレーニングはグループ形式で実施されました。
プロジェクト3「バーチャル・コネクション」では、HDM受給者および集合給食受給者へのトレーニングに加え、「介護者トレーニング」という新たな戦略が実施されています。どの戦略がどのような状況で有効であるかを学ぶため、3つのモデルすべてがミシガン州の6つの異なる郡で同時に実施されています。デジタルリテラシーのトレーニングプログラムは、高齢者の遠隔医療の利用を増やし、介護機関とバーチャルケアプロバイダーを結びつけることが期待されています。技術面や人材面での課題はあるものの、デジタルリテラシープログラムは家族のつながりを深め、孤独や社会的孤立を軽減し、高齢者の生活の質を向上させています。今後の計画には、アクセシビリティを高めるために地域社会に根ざした企業と提携してデジタルリテラシー研修を提供すること、マイノリティや支援が届きにくい人々にも手を差し伸べること、他の郡にも拡大することが含まれています。
- 信頼関係があれば、高齢者がデジタルリテラシープログラムに参加する意欲を高めることができます。
- 地域社会の状況に合わせて、また地域社会のリソースを活用しながら、さまざまなデジタル能力強化戦略を実施することができます。
Freddolino博士のプレゼンテーションの後、Rohid議長は、さまざまな状況で実施されている地域社会ベースの社会イノベーション(CBSI)プログラムを評価しました。また、拡大展開に適した状況を特定することの重要性を強調しました。参加者の選定に関しては、当初はテクノロジーに精通していなかった参加者が、HDMの配送員から受け取った情報に基づいて参加しました。コーチングを通じて築かれた社会的関係が、参加者のプログラム継続を促進した可能性があります。デジタルリテラシー研修に対する家族の支援に関しては、詐欺や詐欺行為に対する家族の懸念が、一部の高齢者のプログラム参加を妨げている一方で、高齢者のデジタル技術の活用に価値を見出す家族もいると演者は述べました。デジタルスキルのレベル評価に関する質問に対して、演者は、g-mailや写真などの基本的な操作スキルは各セッション後にテストされると説明しました。
プレゼンテーション2:シンガポール北東部の町における高齢化社会を支えるコミュニティの強化
2番目の演者は、シンガポール大学社会科学部(SUSS)プロジェクトマネージャー、シンガポール北東部地域開発協議会地区評議員、シンガポール在住の老年学者であるElizabeth Teo 氏(理学修士)でした。 Elizabeth 氏は、シンガポールにおけるDIHAC研究の共同主任研究員であるCarol Ma 教授とともに、能力開発トレーニングの構築に意欲的に取り組んでいます。彼女は夫と共に進行中のプロジェクトを立ち上げました。地域社会強化プロジェクトはシンガポール北東地域開発協議会の町内会を拠点としています。シンガポールは多民族国家であり、各集合住宅には異なる人種グループが居住しています。パンデミック発生前、Elizabeth氏と地域社会のボランティアは、高齢者、低所得世帯、介護施設を対象に、食料や公共料金の支援を行う地域社会強化プログラムを実施していました。パンデミック発生中は、すべての活動がオンラインで行われました。物理的な接触が減り、社会的孤立が生じました。これを防ぐため、また高齢者の健康状態を確認する目的も兼ねて、食料品や生活必需品が毎週自宅へ届けられました。
しかし、パンデミックの規制が解除された際には、高齢者を社会生活に再び取り戻し、彼らをアクティブエイジングにつなげておくことが重要となりました。そのため、「コミュニティフリッジ」プログラムが立ち上げられ、高齢者に継続的な社会的支援を提供し、彼らの社会的つながりの再構築を支援しています。コミュニティフリッジは65歳以上の高齢者が居住する集合住宅に設置されています。スーパーや商店から救出した食品や野菜、コミュニティ・ガーデンで収穫された農産物が集められ、困っている人なら誰でも利用できるようになっています。食品や野菜の入ったフリッジが高齢者の居住区に置かれているため、高齢者たちは責任感と自覚を持って管理しています。高齢者はボランティアとともに、食品の詰め替えや保管、コミュニティフリッジのメンテナンスを行っています。毎週土曜日には、高齢者たちが食品を手に入れるだけでなく、友人や近隣住民との交流を求めてフリッジに集まります。 いくつかの居住区では、高齢者たちがフリッジの食品を使って食事を用意し、それを他の人々と分け合っている。 演者は、このプログラムの成功には、支援的なリーダーシップ、地域社会の協力、資金、ボランティアによる継続的な貢献が寄与していると述べました。 高齢者たちは、自分たちの努力がメディアを通じて公に共有されることで、より力を与えられ、認められたと感じ、その結果、より大きな影響をもたらします。
- コミュニティ・フリッジ・プログラムは、高齢者が社会とのつながりを持つ機会を提供し、所有意識を育み、地域活動に参加する目的意識を生み出します。
- また、このフリッジプログラムから派生する副次的な効果として、ソーシャルメディア「WhatsApp」を利用して地域活動に関する連絡や情報交換を行うことで、高齢者のデジタル技術の利用が促進される可能性もあります。
演者は、質問を募り、会議で取り上げられた主な問題について説明しました。詐欺や詐欺行為を防止するための正式なデジタルリテラシー研修プログラムに関しては、シンガポール情報メディア・デジタル庁(IMDA)が「デジタル大使」を養成し、地域レベルで高齢者のデジタル機器に関する問題の解決を支援しています。コミュニティフリッジは、デジタル大使を通じて、参加者同士が情報を共有する機会となっています。食事の準備における食品衛生と安全性に関しては、高齢者は地域の規則に従い、食品は持ち帰らずにテーブルで提供されます。食事の準備にあたっては、文化や宗教的な要素が考慮されています。WhatsAppなどのソーシャルメディアは、プログラムに関する情報の共有やイベントの計画に活用されています。参加者の一人は、エンパワーメント評価や成功事例の記録を通じて評価を行うことができると提案しました。
最後に議長は、食料や食事は、人種、民族、世代を超えて高齢者を結びつける独特な要素であると総括しました。第一に、高齢者の声や選択に耳を傾けることが重要です。第二に、高齢者にとって、社会的健康、すなわち社会的つながりや孤独感の軽減は、身体的・精神的健康と同様に重要です。最後に、変化の評価や介入の効果の測定には、多面的なアプローチが必要となりうります。4月に開催予定の第28回DIHAC会議の告知をもって、会議は盛況のうちに終了しました。
References
- Services, Michigan Department of Health & Human Services., Home-Delivered Meals (Wheels on Meals).
- Hänninen, R., S. Taipale, and R. Luostari, Exploring heterogeneous ICT use among older adults: The warm experts’ perspective. New Media & Society, 2021. 23(6): p. 1584-1601.
Report:
・後藤夕輝 M.D., Ph.D.,東京科学大学 東京都地域医療政策学講座助教,日本医療政策機構プログラムスペシャリスト
・小柳祐華 Ph.D., 東京有明医療大学保健医療学部講師,順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘルスリサーチ講座非常勤助教
・ミョーニエン アング M.D., M.Sc., Ph.D. 順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘルスリサーチ講座准教授、健康総合科学先端研究機構准教授、国際教養学部准教授
