第29回 DIHAC 研究会 報告 29th DIHAC cross-cultural exchange meeting analysis report (Japanese)
第29回 DIHAC異文化交流会議 実施報告書
タイの社会的企業とマレーシアの学術機関が主導する健康的な高齢化に向けたデジタルリテラシー教育
後藤夕輝, 小柳祐華, ミョーニエンアング
Report in English Report in Thai Report in Spanish Report in Vietnamese Report in Korean
デジタル・インクルーシブ・ヘルシー・エイジング・コミュニティ(DIHAC)は、主に日本、韓国、シンガポール、タイを拠点として展開する多文化間研究プロジェクトです。現在はインド、ベトナム、マレーシア、へ拡大し、関心を持つネットワークや協力を通じて欧州諸国の参画も計画しています。隔月で、世界各国から健康長寿とデジタルインクルージョンの分野におけるイノベーションや地域実践事例を共有する多文化間会議を開催しています。2025年6月18日に開催された第29回DIHAC国際会議では、東南アジア(タイとマレーシア)から講演者が参加し、デジタル技術が高度に発展した社会における健康長寿の事例を紹介しました。
DIHAC研究の責任者であるDr. Myo Nyein Aung准教授が、参加者を歓迎しました。会議には、日本、大韓民国、シンガポール、タイ、マレーシア、中国、インド、ベルギー、オランダ、イタリア、ヨーロッパ、アメリカ合衆国から、公的・民間セクターのステークホルダー、国連職員、大学教員、健康長寿の専門家、研究者、大学院生・学部生など、グローバルヘルス、公衆衛生、社会老年学、ジェロントロジーの分野から50名を超える参加者が集まりました。
第29回DIHAC会議は、スイス国際電気通信連合(ITU)電気通信開発局デジタルインクルージョン課課長兼シニアプログラムオフィサーのMs. Roxana Widmer-Iliescu氏を会議議長として迎えました。Widmer-Iliescu氏はデジタルインクルージョンの専門家であり、20年以上の経験を有し、高齢者のデジタル社会・経済への効果的な参加を確保するため、デジタルアクセシビリティの促進とユニバーサルデザイン原則の適用に積極的に取り組む戦略的役割を担っています。彼女の開会挨拶では、高齢者のデジタルリテラシーはもはや贅沢品ではなく、生命維持に必要な要素であると指摘しました。彼女は、デジタルインクルージョンを市民的、経済的、社会的参加と結びついた人権として位置付ける概念を提唱しました。したがって、高齢者や、女性、非識字者、遠隔地に住む人々といった周縁化された集団が直面する障壁に対処するためには、包括的、交差的、世代間連携のアプローチが不可欠です。最後に、彼女は世界中で戦略的イニシアチブと優良事例を共有し、包摂的なデジタル変革を促進するよう呼びかけました。
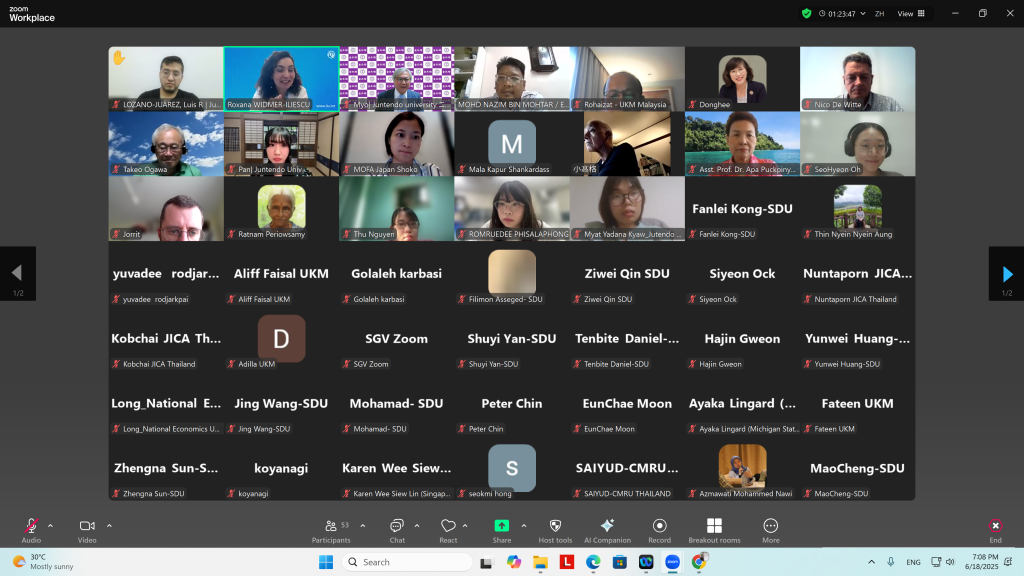
図:29 回目 DIHAC 会議の議長、Ms. Roxana Widmer-Iliescu氏、講演者、国際的な参加者、DIHAC 研究チーム
プレゼンテーション1:タイにおける世代のためのデジタル接続された活動的でインクルーシブなコミュニティの構築
最初のプレゼンテーションは、Young Happy Thailandの共同CEOであるMs. Varissara Klipbua(MSc)によって行われました。Klipbua氏は、高齢者を支援することの重要性についてプレゼンテーションを開始しました。タイでは、COVID-19パンデミック以降、インターネットの利用率とスマートフォンの所有率が急激に増加しています。60歳を過ぎた高齢者は、元の社会的なつながりから孤立する傾向があります。孤独は深刻な健康問題となり、経済的な不利益も伴います。タイ保健促進委員会は、高齢者の生活の質を構成する5つの重要な要素として、健康、環境、社会、経済、技術を挙げています。Young Happyの視点では、デジタル技術を収入創出、健康促進、社会的つながり、日常生活の支援に活用することで、他の要素を改善できると考えています。
Young Happyは、1万人の高齢者ユーザー(1)が参加するオンラインコミュニティ「YH+」を設立しました。このコミュニティは、言語学習、ダンス、デジタルリテラシーなど、多様なオンラインクラスを通じて学習、身体活動、社会的つながりの機会を提供しています。これらのクラスは高齢者に新たな日常のルーティンを創出し、頻繁に参加するユーザーは自己動機付けと日常の目標設定において著しい向上を遂げています。最近、タイの高齢者の経済的生産性を維持するためのオンライン求人掲示板が立ち上げられました。議論では、資金調達とモデルの持続可能性、オンライン安全対策が取り上げられました。YH+のオンライン会員は、無料の1ヶ月トライアル後、月額約200バーツ(約7ドル)の料金が設定されており、比較的リーズナブルです。サイバーセキュリティは、管理者やファシリテーターによって対策され、詐欺防止と安全なデジタル環境の確保が図られています。
- 高齢者向けのオンラインコミュニティは、高齢者の結びつきを強化し、社会的参加を促進する可能性を秘めています。
- 高齢者を対象としたデジタル配信のグループ活動は、自己動機付けと毎日の目標設定を促進し、目的のある健康な高齢化に導きます。
- YoungHappyは、若手の起業家の貴重なリソースを活用してデジタルインクルージョンと健康な高齢化を促進するソーシャルスタートアップ企業の例です。
プレゼンテーション2:マレーシアにおける高齢者のためのデジタルインクルージョンの強化(対象を絞ったトレーニングと実施を通じて)
2人目の講演者は、マレーシア・プトラ大学(Universiti Putra Malaysia)のマレーシア老化研究研究所(MyAgeing®)副所長であるTs.Dr. Mohad Nazim Bin Mohtar博士(PhD)でした。彼のプレゼンテーションは、マレーシアの人口高齢化とマレーシアの高齢者向けデジタルリテラシー促進策に焦点を当てた内容でした。マレーシアは人口高齢化が進んでおり、2020年時点で総人口の10.3%が60歳以上です(2)。ペラ州は高齢者割合が最も高く15.4%であり、マレーシア華人の5人に1人が高齢者です。2019年のマレーシア人の平均寿命(LE)は74.7歳、健康寿命(HLE)は65.7歳でした。高齢人口の地理的・民族的な不均衡な分布、およびLEとHLEの年数差は、マレーシアの医療システムに課題をもたらしています。しかし、これらの課題を機会と責任として捉え、デジタル技術が実現可能な解決策として活用されています。
MyAgeing®が実施するデジタルリテラシープログラムは、高齢者が生涯学習を実践できるように支援しています。2002年に設立されたMyAgeing®は、活発で生産的な高齢化を支援するための研究を行う国家研究機関です(3)。国連人口基金(UNFPA)、マレーシア政府、マレーシアの大学と協力して、複数のデジタルリテラシーパイロットプログラムが実施されました。これらのプログラムは、高齢者に対しデジタルデバイスの知識、基本的なデジタルスキル、デジタルコミュニケーションスキルを習得させることを目的としています。COVID-19パンデミック期間中、高齢者のデジタルインクルージョンを促進するため、自己学習型のデジタルリテラシープログラムが開発されました。現在までに5つの教育モジュールが開発されています。学習モジュールは、デジタルデバイス、ナビゲーション、コミュニケーション、オンラインショッピング、デジタル金融サービス、セキュリティをカバーしています。しかし、高齢者層においてデジタルデバイスの所有率とインターネット利用率の格差は依然として存在しています。主な障壁には、アプリのユーザーインターフェースの複雑さ、自信の欠如、および高齢者の興味の低さが挙げられます。最後に、Mohtar教授は、健康で活発かつ生産的な高齢者を育成し、相互学習と支援のための世代間協力を促進するプラットフォームの必要性を強調しました。デジタルリテラシーモジュールの資料は、こちらで入手可能です
- デジタルリテラシープログラムは、高齢者がデジタルヘルス、ソーシャル、金融サービスを利用するための必要なスキルを身につけるために、適切なタイミングで提供されています。
- アプリケーションのユーザーフレンドリーな設計、高齢者のデジタル環境への参加意欲は、マレーシアにおけるデジタル格差を埋めるために不可欠です。
結論として、議長は、高齢者のデジタルインクルージョンは社会的課題であると同時にビジネス機会でもあると強調しました。高齢者は、その知恵と経験を生かして、デジタルコミュニティの積極的な参加者となることができます。さらに、セクター間および世代間の協働は、デジタルインクルーシブな社会を実現するために不可欠です。最後に、Myo准教授が会議を締めくくり、次回の会議は2025年8月に開催予定であることが伝えられました。
References
- YoungHappy Thailand. 2025 [Available from: https://younghappy.com/.
- data.gov.my. Population Table: Malaysia [Internet]. 2025 [cited June 19]. Available from: https://data.gov.my/data-catalogue/population_malaysia.
- Universiti Putra Malaysia. Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing®) 2025 [Available from: https://myageing.upm.edu.my/.
Report:
・後藤夕輝 M.D., Ph.D.,東京科学大学 東京都地域医療政策学講座助教,日本医療政策機構プログラムスペシャリスト
・小柳祐華 Ph.D., 東京有明医療大学保健医療学部講師,順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘルスリサーチ講座非常勤助教
・ミョーニエン アング M.D., M.Sc., Ph.D. 順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘルスリサーチ講座准教授、健康総合科学先端研究機構准教授、国際教養学部准教授
