第30回 DIHAC 研究会 報告 30th DIHAC cross-cultural exchange meeting analysis report (Japanese)
第30回 DIHAC異文化交流会議 実施報告書
AIとIoTを活用した健康な高齢化の促進:韓国のAIケアコールと日本のフレイル予防のためのAI研究
後藤夕輝, 小柳祐華, ミョーニエンアング
Report in English Report in Thai Report in Spanish Report in Vietnamese Report in Korean
デジタルインクルーシブ健康長寿コミュニティ(DIHAC)は、日本、大韓民国、シンガポール、タイを主要拠点とする多文化間研究プロジェクトです。さらにインド、マレーシア、ベトナム、欧州諸国などへの拡大を進めています。私たちは2か月ごとに多文化間交流会議を開催し、学際的な学びの機会を創出しています。DIHAC会議は2025年8月21日に第30回を迎えました。本会議では、世界有数の超高齢社会である日本と大韓民国が、健康長寿のためのAIとIoTの最新活用事例を発表しました。
DIHAC研究の主任研究者であるMyo Nyein Aung准教授(順天堂大学 グローバルヘルス研究部門)が参加者を迎え、会議を開始しました。40名を超える参加者には、グローバルヘルスと公衆衛生の研究者、大学教員、臨床医、外務省関係者、アジア太平洋地域アクティブエイジングコンソーシアム(ACAP)のメンバー、地域関係者、国際NGOの代表者、日本、大韓民国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、インド、アフリカ、ベルギー、スイス、ウクライナ、イタリア、イギリスからの大学院生・学部生が含まれ、活発な議論が行われました。
第30回会議の議長として、Dr. Donghee Han(PhD、Research Institute of Science for the Better Living of the Elderly所長)を招聘しました。彼女は釜山広域市高齢者政策委員会委員長、ACAP理事兼韓国代表、韓国老年学会会員を務めています。
Han博士は開会挨拶において、「サイバー家族」に関する自身の研究を紹介し、高齢者をデジタルでつなぐ重要性を強調しました。また、高齢者の実体験の意義に触れ、韓国におけるデジタル政策が弱者層をいかに包括的に取り込もうとしてきたかを説明しました。さらに、ベストプラクティス構築に向けた協働の重要性と、デジタル・インクルージョンが高齢化社会を再構築し、人生後半期の質を高める可能性についても述べました。
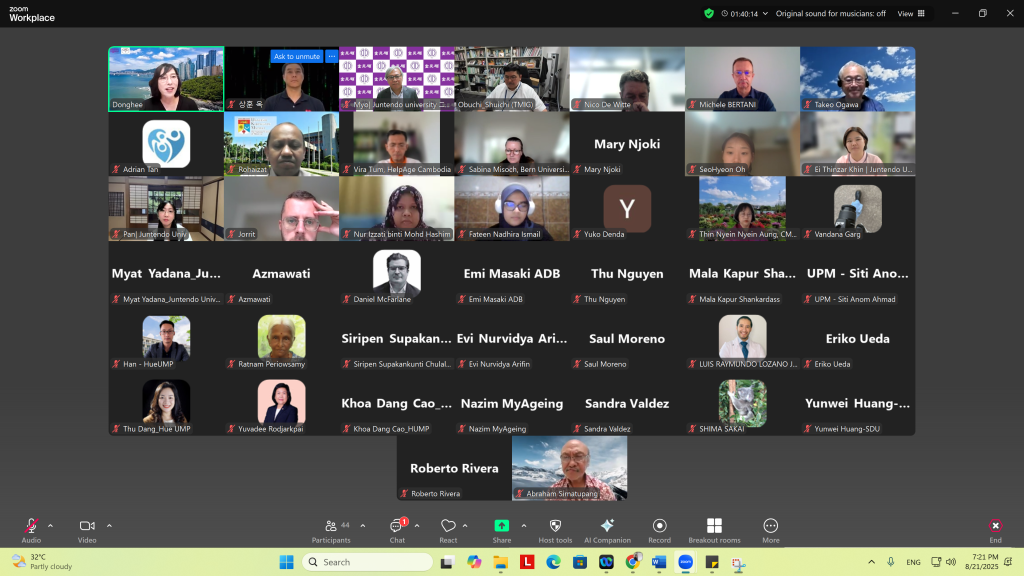
図:30 回目 DIHAC 会議の議長、Dr. Donghee Han氏、講演者、国際的な参加者、DIHAC 研究チーム
プレゼンテーション1:AIケアコールと健康な高齢化(大韓民国)
最初の発表者は、大韓民国NAVER CloudのCLOVAケアコール事業リーダー、Sang-Houn Ok氏でした。Ok氏は、NAVER Cloudが開発したAIベースの電話サービス「CLOVAケアコール」について説明しました。CLOVAケアコールは追加機器を必要とせず、電話での自然な会話を通じて一人暮らし高齢者の安全・健康・情緒状態を確認するサービスです。
韓国では急速な高齢化が進み、2025年には約230万人の高齢者が一人暮らしになると予測されています(1)。新型コロナウイルス感染症の流行は社会的孤立を深刻化させ、従来の介護システムにも影響を及ぼしました。CLOVAケアコールは、定期的なAIによる安否確認を通じて情緒的つながりを提供し、健康問題の早期発見を可能にしています。登録高齢者にAIが定期的に電話をかけ、応答内容を分析してケアコーディネーターや福祉機関へ報告します。主要機能として「個人最適化された対話」のための長期記憶機能を備え、参加自治体全体で90%を超える応答率を達成しています。
Nature Scientific Reports(2025年)に掲載された研究では、CLOVAケアコールを7か月間利用した認知症患者において、記憶力の改善と抑うつ症状の軽減が確認されました(2)。本サービスは国際的にも拡大し、日本では「NAVERケアコール」として出雲市と提携し、文化的違いを超えて好評を得ています。さらに大阪・関西万博2025ではデジタル・インクルージョンのモデルとして紹介されました。2021年のサービス開始以来、CareCallはIoTや医療システムとの連携を進め、個別ケアや緊急時対応を支援する機能へと進化しています。
CLOVA Care Callは第16回DIHAC会議で初披露され、第23回会議で最新情報が報告されました。
- 簡易AI電話サービスは高齢者の安心感を高める一方、スマートフォンとインターネット環境が必要であるためデジタル格差は依然として課題です。
- 高齢者のウェルビーイングにおいて、情緒的ケアとデジタル・インクルージョンが重要であることが強調されました。
- 日本の出雲市への展開は、AI技術による健康的高齢化促進の幅広い受容を反映しています。
プレゼンテーション2:老年学におけるIoTとAIの活用(日本)
第二の講演者は、東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム研究部長の大渕修一氏(PhD, MS, PT)でした。大渕氏は、日本におけるIoT・AI技術の老年学応用について報告しました。2005年の介護保険制度改革以降、日本では要介護リスクの高い方を対象にフレイル予防プログラムが導入されました。しかし参加率は10%未満にとどまったため、研究チームは早期導入者に着目しました。1,500名以上の高齢者を対象とした4年間のコホート研究により、歩行関連指標が機能低下の強力な予測因子であることを明らかにしました(3)。
この知見を基に、チームはスマートフォンを用いた歩行測定法を開発し、東京都の支援を得てスマートウォッチ、センサー、GPSなどを活用したデータ収集を拡大しました。本プロジェクトには在宅高齢者6,000名と外来高齢者500名が参加し、90日間のライフログデータからフレイルと睡眠・歩行・会話パターンの変化との関連を解明しました。特に、食事時の介護者との交流が社会的関与に影響を与える可能性が示されました。機械学習による分析でAUC 0.91のフレイル予測モデルを構築しました(4)。
さらに「タペストリー分析」により、1か月分の分単位生活習慣データを可視化し、参加者を6つのクラスターに分類しました。歩行時間と会話時間が長いクラスター0は、非フレイルと関連していました。
継続的モニタリングは臨床現場における長期追跡を支援し、フレイルの早期発見と個別介入による予防を可能にします。行動変容を促すため、研究チームはスマートフォンアプリを開発し、日々の「フレイル予防スコア」を算出、月次カレンダーで個別フィードバックを提供しています。本アプリには、生活様式を動物に例えたメタファー、健康行動を促すポジティブフィードバック、家族や介護者とのQRコードによるデータ共有機能が搭載されています。
最後に、発表者はタブレット端末を用いた認知機能評価ツール「CompBased-CAT(Computer-Based Cognitive Assessment Tool)」を紹介しました(5)。
- 可視化とメタファーにより、利用者と臨床医双方が生活習慣の変化を客観的に把握でき、早期のフレイル検出と個別介入が可能となります。
- AI・IoTベースの介入は、受動的データ収集と個別化予防戦略を結びつけ、フレイル予防を実現します。
- 高齢者が先進的なデジタルケア技術を採用するには、有用性の認識と使用の容易さが重要な役割を果たします。
第30回DIHAC会議では、日本と韓国の高齢者における健康な高齢化とデジタル・インクルージョン促進を目的としたAI・IoT技術の革新が強調されました。NAVER CloudのCLOVA Care Callや東京都健康長寿医療センターが開発したライフログベースのフレイルモニタリングアプリは、個別化データ駆動型アプローチがケアの隙間を埋め、高齢者がより健康でつながりのある生活を送る力を与える方法を示しています。
スマートフォンとインターネット接続はこうしたサービス利用の前提条件であり、高齢者をオンラインに接続することはもはや選択肢ではなく必須です。インターネットアクセスとデジタルリテラシーの確保は、新たなケアモデルへの公平な参加を可能にする鍵となります。
最後に、PIのMyo博士は、2025年10月に開催予定の「第31回DIHAC会議」について発表しました。
References
- Statistics on the Aged 2024 [Available from: https://kostat.go.kr/boardDownload.es?bid=11759&list_no=433631&seq=1.
- Kang S, Lee Y, Kim N, Ok S-H, Kim P, Park O-H, et al. Beneficial effect of artificial intelligence care call on memory and depression in community dwelling individuals with dementia. Scientific Reports. 2025;15(1):27116.
- Obuchi SP, Kojima M, Suzuki H, Garbalosa JC, Imamura K, Ihara K, et al. Artificial intelligence detection of cognitive impairment in older adults during walking. Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. 2024;16(3):e70012.
- Shuichi Obuchi HK, Rui Gong. Promoting the health of older adults through the utilization of digital devices such as smartwatches –Detection of frailty signs using life-log data 2025 [Available from: https://www.tmghig.jp/research/en/etopics/archives/016559/.
- Chen J-Y, Kawai H, Takahashi J, Ejiri M, Imamura K, Obuchi SP. Test–retest reliability of the computer-based cognitive assessment tool for community-dwelling older adults in Japan: The Otassha study. DIGITAL HEALTH. 2025;11:20552076251317627.
Report:
・後藤夕輝 M.D., Ph.D.,東京科学大学 東京都地域医療政策学講座助教,日本医療政策機構プログラムスペシャリスト
・小柳祐華 Ph.D., 東京有明医療大学保健医療学部講師,順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘルスリサーチ講座非常勤助教
・ミョーニエン アング M.D., M.Sc., Ph.D. 順天堂大学大学院医学研究科グローバルヘルスリサーチ講座准教授、健康総合科学先端研究機構准教授、国際教養学部准教授
